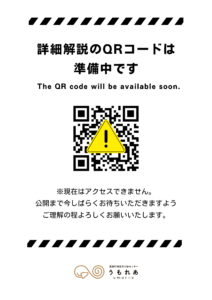考古学旧石器時代– category –
-

洗峰A遺跡
-

加用中条A遺跡
-

正面ヶ原D遺跡
-

胴抜原A遺跡
-

米原遺跡
-

人類の出現と拡散<旧石器時代>
ユーラシア大陸の東端に位置する列島は、最寒冷期によって海水面が100m前後下がった場合、ユーラシア大陸の一部と化す。東アフリカの大地溝帯で発生した人類が、ホモ・サピエンスとしてユーラシア大陸に拡散した時期が約6万年前と考えられている。日本列... -

人類文化はどこまで遡るのか
芹沢長介は、石澤寅二から米原遺跡を案内受け、米原の高位段丘を踏査したことを話して頂いたことがあった。その際に、遺物観察と大地踏査を記録した野帖を見せて頂いた。そこには、斜軸尖頭器のスケッチがあったことを鮮明に記憶している。 中村由克は... -

打ち割りによって石器を作る
-

旧石器時代の活動範囲と道具
土器の無い旧石器時代は、約3万年前から約1万6千年頃までの寒冷気候の中にあった。旧石器時代の人々は、約1万4千年もの長い時間、狩猟採集で食料を獲得し、生や蒸す、焼くなどの料理加工することで食生活を維持してきた。寒冷な気候では、縄文時代のよう... -

第Ⅰ期石器群
-

第Ⅲ期石器群 初源期に流入する2つの石器群
長野県境を流れる志久見川水系には、良質な無斑晶ガラス質安山岩が産出し、川原で人頭大から拳大の原石が容易に採取できる。この右岸に加用中条A遺跡としぐね遺跡が立地する。 加用中条A遺跡は、瀬戸内系石器群の担い手たちが無斑晶ガラス質安山岩を求... -

第Ⅲ期石器群 初源期の遺跡
桾沢(ぐみざわ)遺跡は、神山型彫器を保有するが杉久保型ナイフが無く、素材打面を広く残し先端部を斜めに加工する斜断ナイフ形石器が組成する。類似の遺跡が芦ヶ崎入り遺跡や楢ノ木平遺跡である。 楢ノ木平遺跡は、中村孝三郎が昭和35年に発掘し、「楢...

-1024x730.jpg)