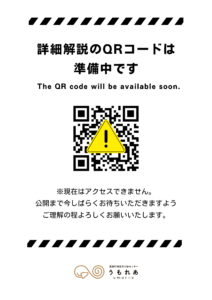土器の無い旧石器時代は、約3万年前から約1万6千年頃までの寒冷気候の中にあった。旧石器時代の人々は、約1万4千年もの長い時間、狩猟採集で食料を獲得し、生や蒸す、焼くなどの料理加工することで食生活を維持してきた。寒冷な気候では、縄文時代のようにクリやクルミなどの堅果類は無く、針葉樹林の林床に生えるベリー類やキノコのほか、シカやクマなどの中型動物を仕留めて得る肉が主食であった可能性があるが、その実態は不明である。
旧石器時代の苗場山麓は、現在の地形と異なり、低位段丘である大割野段丘Ⅰ・Ⅱ面は形成されておらず、正面面の段丘端部ほとりに中津川や信濃川が流れていた。景観は現在の尾瀬沼のように針葉樹の森が広がり、降雪は1m程度であったと推測できる。
すなわち、旧石器時代の人々は、生業活動に合わせ移動し、石器の石材を獲得しながらのジプシー的な生活であった。清津川や中津川、志久見川は石器石材が豊富に採取される河川であることから、多くの旧石器時代の人々が往来し、時には接触することで情報や生殖環境の交換が行われていたとも推測される。
特に狩猟を想定するならば、陥穴などの罠猟のほかに、狩猟具として刺突具(石製槍)の発達史が認められる。苗場山麓では、先の尖る剥片を意図的に剥離し、その打面部を残し、その端部の一部に加工を施す初期的な尖頭器がⅠ期に出現する。Ⅱ期の遺跡は確認できておらず、実態は不明である。Ⅲ期になると細く長い剥片を剥離し、その剥片の打面を残し、先端部を斜めに断ち切るような斜断ナイフ形石器が出現する古相段階がある。中相段階になると剥片の先端と基部を尖らす加工を施す杉久保型ナイフ形石器が現れ、神山型彫器とセット化する。新相段階になると、素材剥片が小形化する傾向からナイフ形石器も小形化する傾向がある。また、客体的に関東地方で展開してきた二側縁加工ナイフ形石器や上ゲ屋型彫器が石器組成に組み込まれる現象が現れる。このⅢ期は地方化が進行した時期であり、基本的に杉久保系石器群が展開していたといえる。また、Ⅲ期古相段階に、瀬戸内系石器群が流入する現象がある。この瀬戸内系石器群の担い手たちは、無斑晶ガラス質安山岩を目的に産地である志久見川水系に入り込み、活動を展開していたことが加用中条A遺跡や今井城跡、赤沢城跡、正面ヶ原B遺跡などで確認できる。さらに古相段階と推測されるが有樋尖頭器と呼ぶ尖頭器先端部片面に樋状剥離を施す特異な尖頭器を作出する集団が信州地方から多量の黒曜石と共に、流入したと考えられる。彼らは細原型彫器と呼ぶ特異な形態の彫器を使う特徴がある。
Ⅲ期の石器製作技術の蓄積を背景に、厚い横長剥片を巧みに加工して優美な両面加工尖頭器を作り上げる段階に到達する。これがⅣ期である。Ⅳ期では、剥片の部分加工や片面加工によって両端部が尖る尖頭器を製作する一方、巧みな剥片加工技術を背景に両面加工を施す尖頭器が組成する段階を経て、両面加工の尖頭器が普遍化する。
 オオシラビソ
オオシラビソ
参考文献
佐藤雅一ほか 2017 『本ノ木-調査・研究の歩みと60年目の視点-』 津南町教育委員会