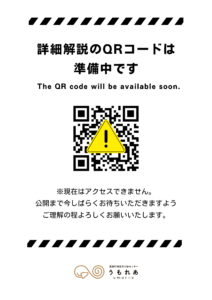崖線から湧き出る大清水の豊富な水が流れる小川の岸辺に、竪穴住居群がまとまって検出された。集落全体から見るならば東端に当たる場所である。右岸の竪穴住居群が立地する平坦面は、小川の流れに近接する。左岸の住居跡群が位置する段丘端部と小川の比高は、約7mである。すなわち、住居跡が立地する標高にやや違いがある。
この小川が流れる沢地形から大量なトチノキの実(内皮)が大量に堆積していたことから、トチノキの実を対象とした渋晒(しぶさらし)作業が行われていたと考えられる。
この円形を呈する竪穴住居跡群は、幾度となく、切り合う程度の移動範囲の中で建て替えを繰り返していることが分かる。広い大地に移動することなく、小川が流れる両岸に占地する必要性があったと推測される。それがトチノキの実を対象とした水晒作業と深く関わる可能性がある。さらに、興味深いことは、右岸の竪穴住居跡から焼土と炭化材に混じり、石剣や石冠などの「第2の道具」が偏在(集落全体)して出土した。この水辺で儀礼的行為が行われていた可能性がある。







参考文献
佐藤雅一ほか 2014 『魚沼地方の先史文化』 津南町教育委員会