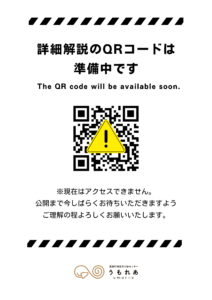人々の活動痕跡が残された場所が遺跡である。生業活動を背景に残される活動は、その目的によって多様である。また、活動は移動しながら点々の残されたと推定されるが、それらは連鎖的な活動である。すなわち、残されている小規模な活動痕跡の同時性があり、同一集団の活動痕跡として検証できれば、広大な地域における連鎖活動を把握し、活動によって残される活動痕跡に違いがあったことを理解することが可能となる。 このように多様性ある活動痕跡の同時性問題は、加藤晋平が進めた、北海道常呂川流域における考察が端緒といえる。この考察から学び、小規模活動痕跡で出土した無斑晶ガラス質安山岩の石核と剥片の接合資料に対して、剥片間の空間に石膏を流しこむことで剥片が復元できる。この剥片を「欠失剥片」として復元することが可能であるが、この欠失剥片は複数枚による集合体、あるいは1枚の剥片である可能性がある。この欠失剥片を復元しておき、周辺開発域の試掘調査などで同一層位から出土した同一石材剥片との比較検証で仮に発見した場合、その剥片を元の接合資料と接合検証して接合した場合、離れた場所で残された活動痕跡を有機的に把握し、その類似性と相違性を導き、同一集団の連鎖活動を描き出すことになると考え実践した遺跡が、魚沼市権現平遺跡である。 この活動から15年、苗場山麓に展開した開発域をくまなく試掘調査し、出土した石器群を同一母岩資料、同質母岩資料に分けて接合関係を検討し始めた。下モ原Ⅰ遺跡の発掘調査が終了し、段丘面が異なる居尻A遺跡を発掘し、整理作業途上、同質母岩資料と考えられる資料が下モ原A遺跡にあることに気が付く。しかしながら、下モ原Ⅰ遺跡と居尻A遺跡の石器群の顔つきが違うことから時間軸が違う予想を持っていたにも関わらず、異なる遺跡の同質母岩資料同士が接合した瞬間であった。標高差40m、水平距離600mの地点に残された石器群が接合したことにより、その石器群は同一集団が残した「同時性のある一括資料」として評価できるようになった。これこそ連鎖行動による活動痕跡の同時性と同一集団の痕跡検証である。 また、同質母岩と同一母岩に階層化して石器群を分析する方法は、1988年の湯沢町大刈野遺跡で考えた分析法である。この際、当時京都大学の山中一郎先生からご教示頂いた。 参考文献 新潟県教育委員会 1985 『下倉山城跡 権現平遺跡 両新田遺跡』 佐藤雅一 1988 『大刈野遺跡』 湯沢町教育委員会 佐藤雅一ほか 1998 「居尻A遺跡」『平成10年度 津南町遺跡発掘調査概要報告書』 津南町教育委員会 佐藤雅一ほか 2000 『下モ原Ⅰ遺跡』 津南町教育委員会