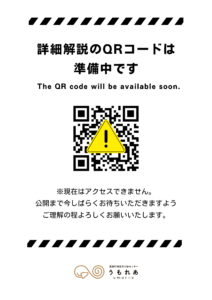文明社会に住む我々が、土偶の本質を含む縄文人たちの精神世界を理解することは不可能である。しかし、世界の狩猟採集民族の思考などを便りに、その実態を垣間見る努力が認められるならば、語りを許していただきたい。
まず、小林達雄が出土した遺物を観察し、機能がおおよそ理解でき、現在の道具に類似する遺物を「第1の道具」と名付けた。すなわち、鏃(石鏃)、掘り具(打製石斧)、伐採加工用斧(磨製石斧)、臼(石皿)などである。しかし、男根を模倣したと推測できる石棒や、石剣、石冠、土偶、三角とう土製品など、機能が予測できない遺物を「第2の道具」と呼んだ。
この「第2の道具」の社会的機能が、縄文人の精神世界と深く交差すると考えられる。自然界とヒトをどのように捉えていたか?自然に順応し、適応して生活していた事実はあろうが、自分たちヒトと自然界は一体と考えていた可能性があり、現代のように自然界を人類が征服し、それを上下の関係で捉えていたとは考えづらい。


参考文献
佐藤雅一ほか 2014 『魚沼地方の先史文化』 津南町教育委員会