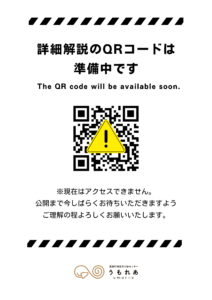桾沢(ぐみざわ)遺跡は、神山型彫器を保有するが杉久保型ナイフが無く、素材打面を広く残し先端部を斜めに加工する斜断ナイフ形石器が組成する。類似の遺跡が芦ヶ崎入り遺跡や楢ノ木平遺跡である。 楢ノ木平遺跡は、中村孝三郎が昭和35年に発掘し、「楢ノ木平型ナイフ」を提唱した遺跡である。この遺跡は長く、杉久保系石器群の遺跡と考えられており、楢ノ木平型ナイフに関して、古相の尖頭器ではないかなど、話題が尽きない遺跡であった。しかし、令和時代に入り、4回調査された楢ノ木平遺跡を総合的に理解する目的で津南町教育委員会は、長岡市教育委員会と郡山女子短期大学の協力を得て、整理調査を実施し報告書を刊行した。この一連の作業によって、神山型彫器を持つが杉久保型ナイフ形石器は保有しない。その様相は、桾沢遺跡や芦ヶ崎入り遺跡に類似し、その特徴は斜断ナイフ形石器を組成することである。また、多くの接合資料が認められ、その剥離工程などの検討と理解が進められた。さらに「楢ノ木平型ナイフ」を尖頭器として理解し、関連する調整剥片があるかを調べたが、それに当たる、類似する剥片は皆無であったことから、報告書では単体で入り込んだ石器と理解し、石器組成から除外して理解を深めた。 神山遺跡は、昭和33年に芹沢長介・麻生優によって発掘調査された。その結果、出土石器群のまとまりを世帯と考え、旧石器時代の社会学的研究が進められた。また、細かな剥離技術や石器形態研究が行われ、杉久保型ナイフ形石器を主体とし、神山型彫器を組成する典型的な杉久保系石器群の標識遺跡として評価された。その後、遺跡は滅したとする記録を踏まえた水田開発計画が持ち上がったが、津南町教育委員会は遺跡が滅した証拠が必要と考え範囲確認調査を実施した結果、当時の調査トレンチ跡を確認し、明瞭な遺物包含層も残存することから、協議を進め、開発事業者のご理解とご協力から開発範囲から除外頂いた。その後、津南町文化財調査審議委員会は町にとって貴重な旧石器時代遺跡であることから、恒久的に保存することを決めて、平成30年に津南町指定史跡に登録した。 参考文献 芹沢長介 1959 『神山』 津南町教育委員会 中山孝三郎 1961 『楢ノ木平遺跡調査報告書』 長岡市立科学博物館考古研究室 佐藤雅一ほか 2005 『町内遺跡試掘確認調査報告書(5)〈谷内地区遺跡群〉』 津南町教育委員会 佐藤信之ほか 2024 『芦ヶ崎入り遺跡―石黒川第2号砂防堰堤整備事業に伴う発掘調査報告書―』 津南町教育委員会 山本克ほか 2025 『楢ノ木平遺跡―第3次調査報告書―』 津南町教育委員会