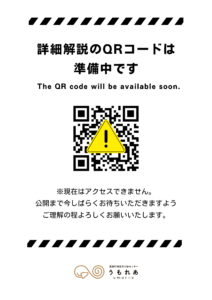第Ⅲ期石器群は、原則「杉久保系石器群」であり、杉久保型ナイフ形石器と神山型彫器がセットとして存在する。しかし、第Ⅲ期古段階とした初源期では、神山型彫器に斜断ナイフ形石器がセット化する。斜断ナイフ形石器は、素材剥片の打面を残す特徴がある。また、楢ノ木平遺跡と神山遺跡との石材構成や石核残存率、剥片の大きさなどから神山遺跡を便宜上、第Ⅲ期の初源期に配置した。隆盛期は数多くの遺跡が苗場山麓で発見されているうち、下モ原Ⅰ遺跡と居尻A遺跡の遺跡間接合資料を展示した。
さて、ここでは終焉期の遺跡を紹介することとする。終焉期は、小形の素材剥片選択に伴う杉久保型ナイフ形石器の小形化や、関東地方の「二側縁加工ナイフ形石器」と「上ゲ屋型彫器」が共伴する資料群が存在することから、仮説的に終焉期を設定して配置した。すなわち、第Ⅲ期石器群のうち、初源期・隆盛期・終焉期の3段階変遷は仮説による試案であり、層位的検証を得ていないものである。言い換えれば、神山型彫器と杉久保型ナイフ形石器を要素として、石器群を把握するならば多様である実態がある。これらを素材の大きさや石材選択、石器組成を要素としてまとめ上げると便宜的に3つのまとまりが指摘でき、それらをあえて時間軸に配置したものである。いみじくも隆盛期とした下モ原Ⅰ遺跡と居尻A遺跡の遺跡間接合を踏まえるならば、これら顔つきの異なる石器群を3段階の棚に意図的に納めることは、批判されるべき行為である。しかし、このたびは空間軸における多様性を理解した上で、議論の活性化を考えてあえて時間軸の配置を試みたことを理解頂きたい。
上原B遺跡は、沖ノ原台地の西側に位置する。すなわち、高位段丘面の湧水沢に近接する遺跡である。神山遺跡と比較すると、素材剥片が幅広く、短い。この素材から杉久保型ナイフ形石器が作られている。そして、神山型彫器を保有する石器群であることから隆盛期より新しい要素であろうと理解した。
新井遺跡は、上原B遺跡の近傍に深く流れ込む馬界川右岸に立地する。上原B遺跡と同様に米原段丘面に所在する。終焉期から第Ⅳ期への過渡的変遷を仮説として考えた場合、尖頭器の発生あるいは流入を想定する必要がある。この新井遺跡では、同質母岩資料に杉久保型ナイフ形石器と尖頭器が含まれていたことが重要な視点である。ナイフ形石器が主体として存在していながらも、同質母岩素材から尖頭器を製作したシナリオである。この杉久保型ナイフ形石器に尖頭器が共伴し、それに神山型彫器の他に「類上ヶ屋型彫器」が伴う事実である。このような一群をあえて仮説的に終焉期に配置することで、今後の議論の活性化に期待したい。
参考文献
佐藤雅一ほか 2021 『新井遺跡』 津南町教育委員会
佐藤雅一ほか 1998 「居尻A遺跡」『平成10年度 津南町遺跡発掘調査概要報告書』
津南町教育委員会
佐藤雅一ほか 2000 『下モ原Ⅰ遺跡』 津南町教育委員会
佐藤雅一ほか 2023 『上原B遺跡』 津南町教育委員会